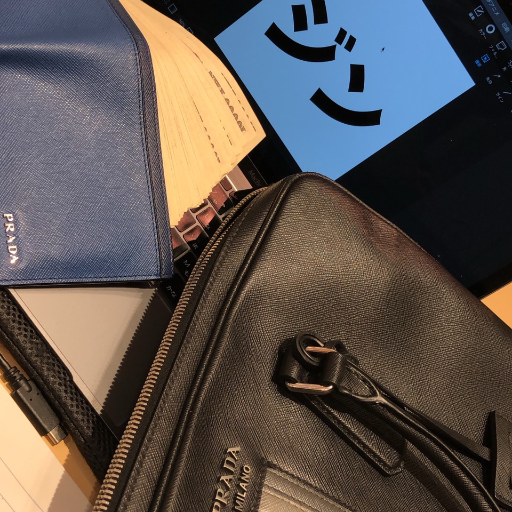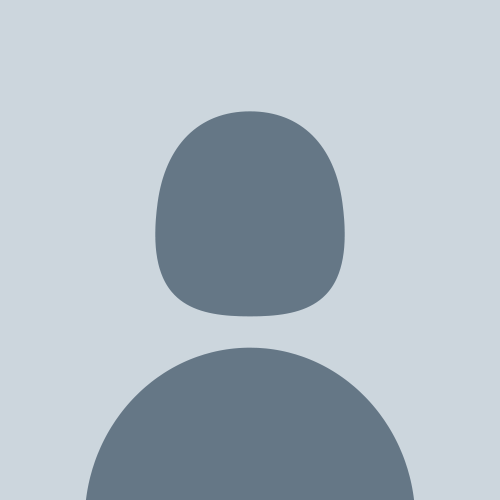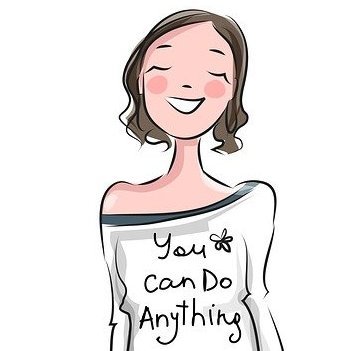偏差値40からの東大早慶合格テク!
@corecom22
(無料相談はhttp://line.me/ti/p/jsgWE_kD5O から)偏差値40台の方に朗報です!偏差値40から東大&慶應に合格した家庭教師2人が、偏差値40からの東大早慶合格テクをまとめました。ぜひ読んでみてください!
You might like
一気に勉強時間を伸ばそうとしなくていい。伸ばせる訳がないし、伸ばせないと挫折感が出て全く勉強できなくなるからだ。そうじゃなくて、1日5分ずつでもいいから確実に勉強時間を伸ばしてほしい。それを積み重ねることによってしか、勉強時間を伸ばすことはできない。
「息抜き」に気を抜いてはいけない。ただ寝てだらだら過ごすだけではなくて、息抜きだからこそ精一杯息抜きをしないといけない。映画をみるとか、音楽を聴くとか、起きながら息抜きをすることで、寝過ごさずに済む。これがとても大切なことなんだ。
他人をライバルにするとつらい。どうしてかというか、他人は自分には制御不能の存在だからだ。自分が成績あがったのに、他人がもっと成績があがったらやはりつらいだろう。それに引き換え、昨日の自分はもう決まってしまった物だし、今日の自分はいますぐ変えられる。制御可能だ。昨日の自分に勝て。
ただ机に坐って勉強しているだけでは、ダメだ。それはべつに勉強の仕方としてダメというよりも、体力的に無理だ。だから歩き回りながら音読するとか、なにかしら身体を動かす工夫が必要だ。勉強は頭だけでやっているわけじゃなくて、身体もあなたの勉強に付き合わされているんだから。
どんな無理に思える目標でも、日々の当たり前の行動によって成就する。逆に、日々無理な目標を立てても、実行が伴わなければ、成就することはない。日々当たり前のことをして、毎日改善することによってしか、無理な目標は達成できない。毎日改善。これが大事。
実際自分がどれだけ分かってるかを確認する仕組みが必要。英単語だけ見て日本語書けるかどうかとか、とにかく書いて確認すること。覚える時は音読が基本だけど、確認するときは書いて確認するのが王道だよね。
自分なりのルールが必要。ぜんぶ終わるまで寝ない。徹夜しても寝ない。とかね。毎日この三つだけはかならずやるとかね。これが守れなかったら死んだ方がいいぐらいの気持ちでそのルールを守る事。ルールを守り続ける事が快感になるぐらいまでルールを守ろう。
やたら整理整頓を強制する人がいるけれど、べつに自分にとって一番過ごしやすい環境でさえあれば散らかっててもいいんだよ。容赦なくゴミ箱に捨てれば片付けにも困らないしね。優秀な人にも整理整頓派とカオス派がいる。どちらでも合格できる。
チョコとかキャラメルとか、小さいものでいいから、勉強15分ごとに1粒食べるとかしてうまく気分転換するといい。すぐ食べられるものがいいね。休みっていうのは、細分化すればするほど疲れが貯まらなくなるからね。疲れる前に休む事だ。
勉強が進まないとき、なにを喜びにしてやる気を出すかというのは難しいもんだ。模試の成績もあがらないし、定期テストの勉強なんかやる意味があるかどうかわからない。そんなときは、なにも勉強してない段階で単語帳の一範囲をテストしてみて、勉強したあとにどれぐらい上がるかを見ればやる気出るよ。
勝つ事へのこだわりっていうのは、点数を取ることへのこだわり。偏差値70あったら入りたい大学に入ろう。大学はいる上で大切なのは、偏差値なんかじゃないから、偏差値なんか無視して行きたい大学選べばいいよ。成績なんかやれば上がるしね。
まあ、地頭次第だけど、やはり苦手科目はどんなにうすのろでも一ヶ月~三ヶ月で片付けるもんだな。それぐらいで片付けきらないと次に進めない。一ヶ月でやる覚悟をもって計画し、あとは微調整ってかんじかな。いずれにせよ三ヶ月あったらものにはなるよ。
基本的に、問題解くスピードっていうのは、1日3問ずつ&直近10日分全問解き直しか、1日5問ずつ&直近7日分全問解き直しか、1日10問ずつ&直近3日分全問解き直しの三つしかないな。これしかない。残された時間と定着度合いを見ながら調整するしかないな。
理系教科はもうだいたい王道パターンは決まってるよな。はじめからていねいにを辞書代わりにしながら、基礎問題精講をさくさく解いて、できれば時間に余裕があれば1日3問ずつ、直近10日の問題はすべて解き直す勢いでね。時間無ければもっとハイペースになるけどね。
答えの丸写しをするのは本当にだめ。答え見ても良いけど、隠して再現できるようにすることがなによりも大事。三回、ないしは十回は解き直そう。それこそ、直近十日分ぐらいの問題はかならず全問解き直すことを習慣にしたほうがいい。間違った部分だけとかぬるい勉強はしない。
化学とかも元素図鑑みたり、物理だったら実験集だけどたとえば空想科学読本とかでんじろう先生とか読んでとにかく興味持つ事だよな。そうすれば、答え読んで、隠して、再現するのも簡単にできるようになる。
過去問って受験生の聖書だからな。とにかく穴が空くぐらいつかわないとね。用語全部抜き出して、参考書のどこにのってるか書いて、どれぐらい網羅してるか確認して安心する。そのプロセスが大事だよな。
遺伝ができなくて悩む人が多いな。解説が分かりにくいのがそもそもの問題だと思う。大森の遺伝問題はすごくわかりやすくていい。グラフ問題もなかなかいい。勉強ができるかどうかってひとえに先生の問題だからな。教え子さんの問題ではない。
理系教科はさ、分野によってやり方変えないといけないよな。文系みたいに暗記一本やりではいかない。演習系と暗記系に勉強を分けないとね。演習系はとにかく問題解いて、過去十日分ぐらいの全問題を解き直すこと。暗記系はそこまでやる必要はないな。
なんのためにそれをするのか、なんのためにそれをしないのか、すべて決める事。まあ、基本やることだな。人生やるかするかだ。そのなかでうまくいったものだけやり切ればいい。すべてやり切ったら時間切れになるし、あまりに効率が悪いからね。
United States Trends
- 1. Jimmy Cliff 9,910 posts
- 2. Good Monday 39.1K posts
- 3. #MondayMotivation 9,910 posts
- 4. TOP CALL 4,234 posts
- 5. Victory Monday 2,132 posts
- 6. AI Alert 1,950 posts
- 7. The Harder They Come 1,092 posts
- 8. Market Focus 2,941 posts
- 9. #MondayMood 1,302 posts
- 10. Check Analyze N/A
- 11. Token Signal 2,523 posts
- 12. #MondayVibes 2,635 posts
- 13. Happy Thanksgiving 11.1K posts
- 14. DOGE 202K posts
- 15. SAROCHA REBECCA DISNEY AT CTW 755K posts
- 16. #centralwOrldXmasXFreenBecky 738K posts
- 17. #NoNeedToSay_MV 69.6K posts
- 18. $NVO 2,287 posts
- 19. Monad 136K posts
- 20. Soles 84.5K posts
Something went wrong.
Something went wrong.