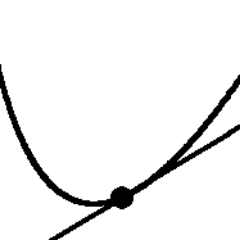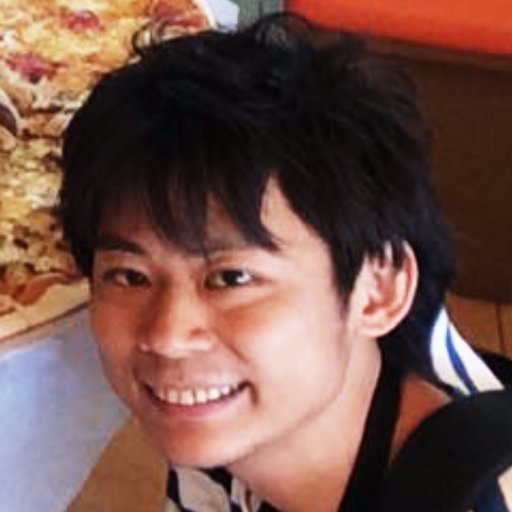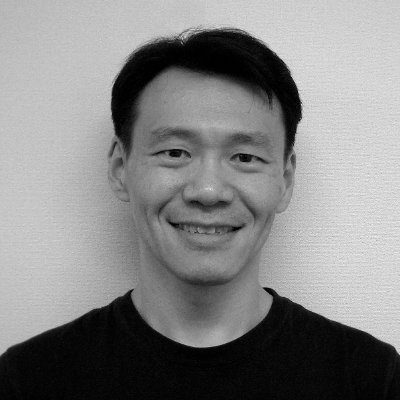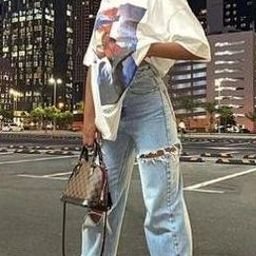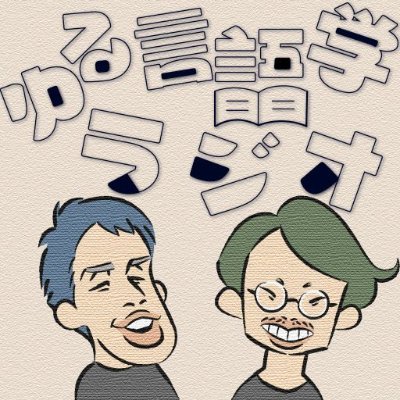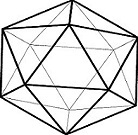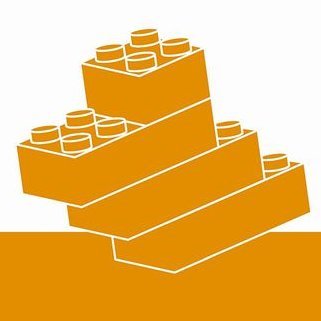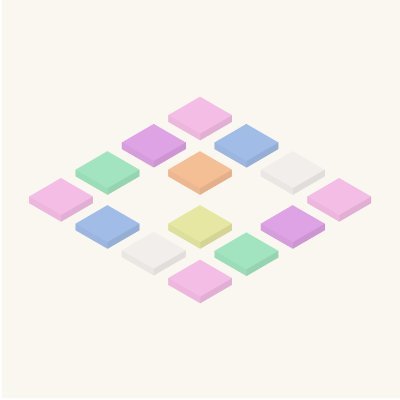Potrebbero piacerti
これは最近痛感するのですが、外部露出したがらない&一社のキャリアが長いみたいなエンジニアはインターネット上では観測しにくいけど妖怪のように各社の深淵に居て、一緒に仕事すると腕の強さにビビったりするので、居るところには妖怪がいます。
ML系の論文を紹介するアカウントっていっぱいあるんだけど,論文を批判的に読めていない有名アカウントがかなりあって,そういう情報を広げられると期待度コントロールの意味でちょっと困る.
論文だったら会議・論文誌にリジェクトされたり後続論文に批判されたりするから(ある意味)健全なんだけど,Twitterアカウントの "論文レビュー" って基本的に批判されないし,論文がおかしいことが判明した後のフォローアップも基本的に行われないから,割と悪質だと思ってる.
博士のアイドルグループPhD48の応募者の男女比に偏りが出てきたので女性限定公募になりました。

統計や機械学習が役に立たないという意味では一切ないので安心して勉強して大丈夫です。超便利です。ただ、データ分析も方法論自体の学習も、当たり前ですが「理解すること」が基本です。実装してできた気になる、本を消化して分かった気になる、はよろしくないです。
そもそも統計手法や機械学習で何かを「立証する」「保証する」っていうのはできなくて、深く考え始めると何もできない感覚がしてきます。個人的には「限られたデータ・情報・時間・費用・計算リソースを活用して精いっぱい妥当な意思決定を行うための方法」くらいに考えています。
(因果推論に限らず)統計手法って学べば学ぶほどできることが増えるんじゃなくて、できないとわかることが増えると思うんだけど、応用の人って後者を意識しないで前者をポケモンを集める感覚で増やすから誤用が増える。
世の中の研究者の大半が理解できてない(誤用してる)概念を高校生にどうやって教えるつもりなんだろ。
「AIが自動で法則性を見つけてくれて精度の高い予測をしてくれる」という文言を見た時点で「そんなアホな」って言ってくれる人が好きです。ここから建設的な議論が始まる。
個人的な経験としては、機械学習や統計なるものに強い疑いを持っている人の方が最終的には一緒に仕事がしやすく、シナジーも生まれやすいですね。
深層学習や機械学習の人たちがある領域に飛び込んできて「革新的な成果」なるものを出しても、よくよく蓋を開けてみれば彼らなりの得意とするゲームに勝っただけというか、領域的にそんなにインパクトなく終わる場合が多い気がする。
道具としての統計は、限られたデータ、情報、時間、コスト、計算資源のもとでせいいっぱいの合理的判断を下すための方法論であり、これを使って何かを「証明」したり「保証」したりするために使うものではないです。
東大の佐藤一誠先生の研究室のページに、研究の方針が書かれていて本当にこれ大事だなと思います。研究のための研究ではなく社会の問題解決に使える技術を作る。 ml.is.s.u-tokyo.ac.jp/about

要は、issueとsolutionの対応付けが、研究とビジネスとでぐちゃぐちゃになってしまっている。研究領域のissueから生じたsolutionを、そのままビジネスのsolutionとして使ってはいけない。
20年以上前のブログ記事ですが、現在からみて過去の話なのか未来の話なのかわからなくなってきますね。 easy.mri.co.jp/19990427.html
“批判の多くは数理モデルへの初歩的な無理解に基づくか…政治的ないし行政的責任との混同に基づく…モデルの仮定が常に現実の多様性をとらえきれていないというのは事実で…あるが、モデルなしに対策するのはスピードメータのない車を運転するようなもの” buff.ly/3g5deHa 稲葉寿さんの訓戒
↓ちなみに個人的に一番好きじゃないのが生物の生態や進化を工学的な最適化に持ち込むっていう話。無理矢理なアナロジーで妙な応用先を探していないで徹底的に進化や知能の創発などの解明に注力していただきたい。
機械学習や深層学習が「ズル」して学習データセットで良い成績を出すという話は結構根深いです。例えば画像中の猫・犬を分類するタスクで、DNNで誤って犬と判定された猫は芝生の上にいたり。学習データ中では屋外の芝生にいるのは犬の方が圧倒的に多かったということなんでしょう。
こういうやり方のダメなところは、誰も解決すべき本質的な課題に向き合ってないことだと思いますね。イノベーションは組み合わせから生まれるとは言いますが、それは外から見た場合であり、中の人間は解くべき課題、解明すべき謎に向かっていないと。
以前,とある企業の取材で白板に中心極限定理が書かれていたのがSNSで総突っ込みされていたけれども,講義をしている感覚からすると世の中のエンジニアに中心極限定理を笑える人はそんなにいないはず.
United States Tendenze
- 1. South Carolina 29.2K posts
- 2. Texas A&M 28.4K posts
- 3. Shane Beamer 3,891 posts
- 4. Ryan Williams 1,348 posts
- 5. #EubankBenn2 13.2K posts
- 6. Michigan 42.9K posts
- 7. Ty Simpson 1,815 posts
- 8. Sellers 13.6K posts
- 9. Heisman 7,676 posts
- 10. Alabama 16.4K posts
- 11. Northwestern 7,288 posts
- 12. Marcel Reed 5,001 posts
- 13. #GoBlue 3,921 posts
- 14. Gio Reyna N/A
- 15. Oklahoma 18.1K posts
- 16. Mateer 1,436 posts
- 17. Sherrone Moore 1,076 posts
- 18. Underwood 3,913 posts
- 19. Jam Miller N/A
- 20. Malachi Toney N/A
Potrebbero piacerti
-
 koron
koron
@koronWCSC -
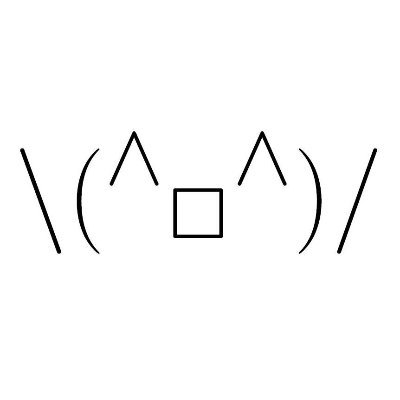 吉田伸生著書📚独学支援✊
吉田伸生著書📚独学支援✊
@noby_leb -
 Daisuke Kurisu
Daisuke Kurisu
@hedrondice -
 鈴田
鈴田
@Ls333FKleC0fwAe -
 Michio Seto
Michio Seto
@MichioSeto -
 サナトリウム🌱虚心坦懐
サナトリウム🌱虚心坦懐
@math095562 -
 Sonobe
Sonobe
@sonobayes -
 伊集院@数学
伊集院@数学
@ijuin_sugaku -
 とら🐯あまがえる文庫🐸
とら🐯あまがえる文庫🐸
@inageshogi -
![miiitomi's profile picture. Yoji Tomita / CyberAgent AI Lab Research Scientist.
経済学/マーケットデザイン/相互推薦/ネイル/読書/競プロ/サッカー🇫🇷⚓️
『[AIと経済学]で もっとよくなる保育政策』発売中! https://t.co/Ob1HKrVOt4](https://pbs.twimg.com/profile_images/1719725453282619392/N2NQbHC6.jpg) みーとみ
みーとみ
@miiitomi -
 すたりむ@カムラッド
すたりむ@カムラッド
@stairlimit -
 宝_Tempari
宝_Tempari
@Treasure_Travi -
 びりお@金これ勢
びりお@金これ勢
@birio_riha -
 鈴木 史馬
鈴木 史馬
@ShibaSuzuki -
 時計の変換
時計の変換
@cdd_1942
Something went wrong.
Something went wrong.

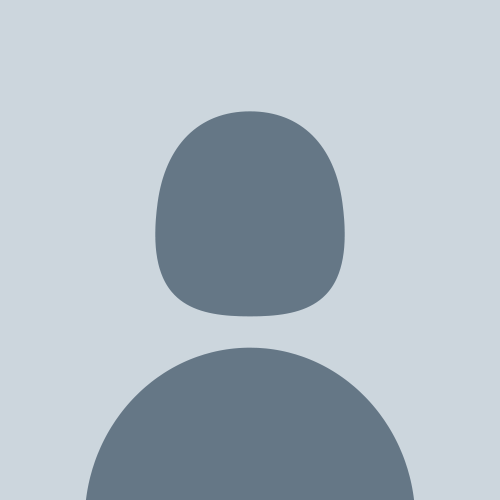









![miiitomi's profile picture. Yoji Tomita / CyberAgent AI Lab Research Scientist.
経済学/マーケットデザイン/相互推薦/ネイル/読書/競プロ/サッカー🇫🇷⚓️
『[AIと経済学]で もっとよくなる保育政策』発売中! https://t.co/Ob1HKrVOt4](https://pbs.twimg.com/profile_images/1719725453282619392/N2NQbHC6_x96.jpg)