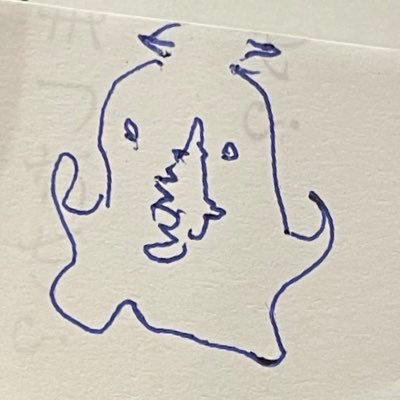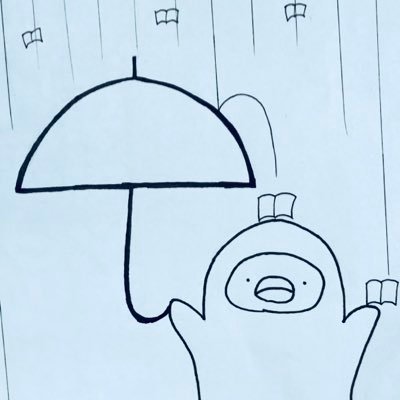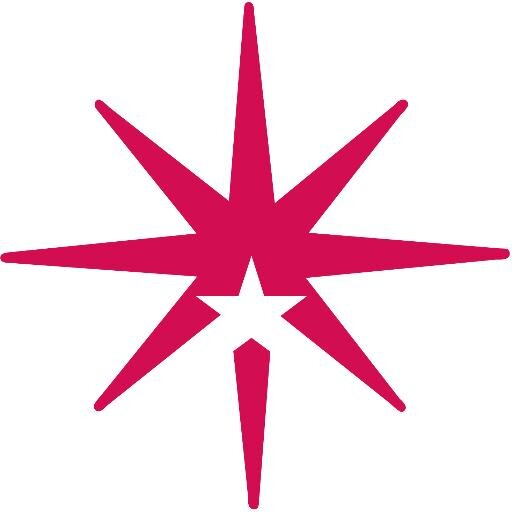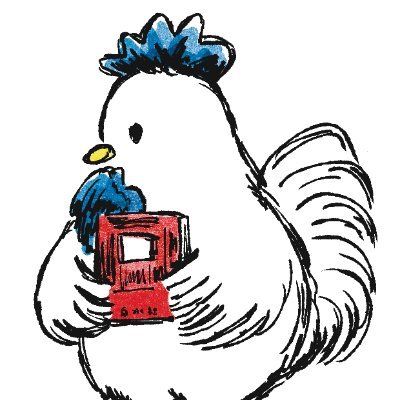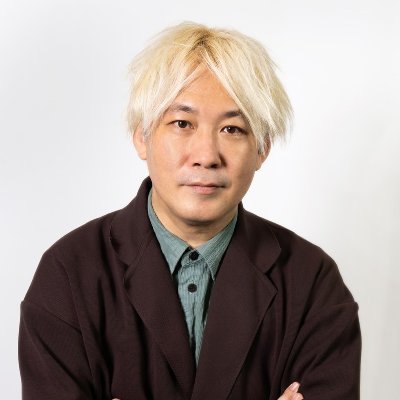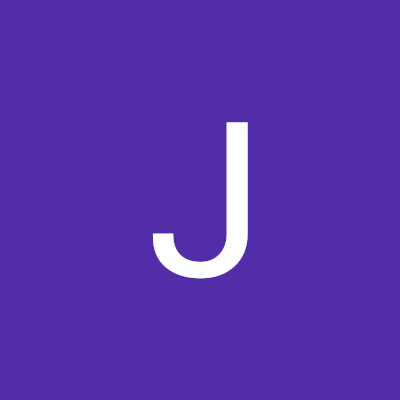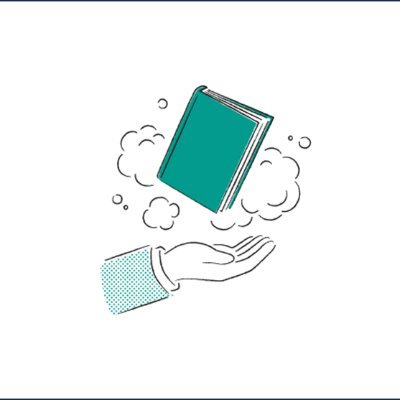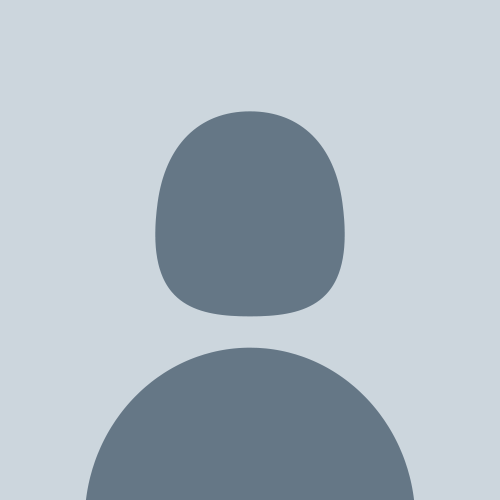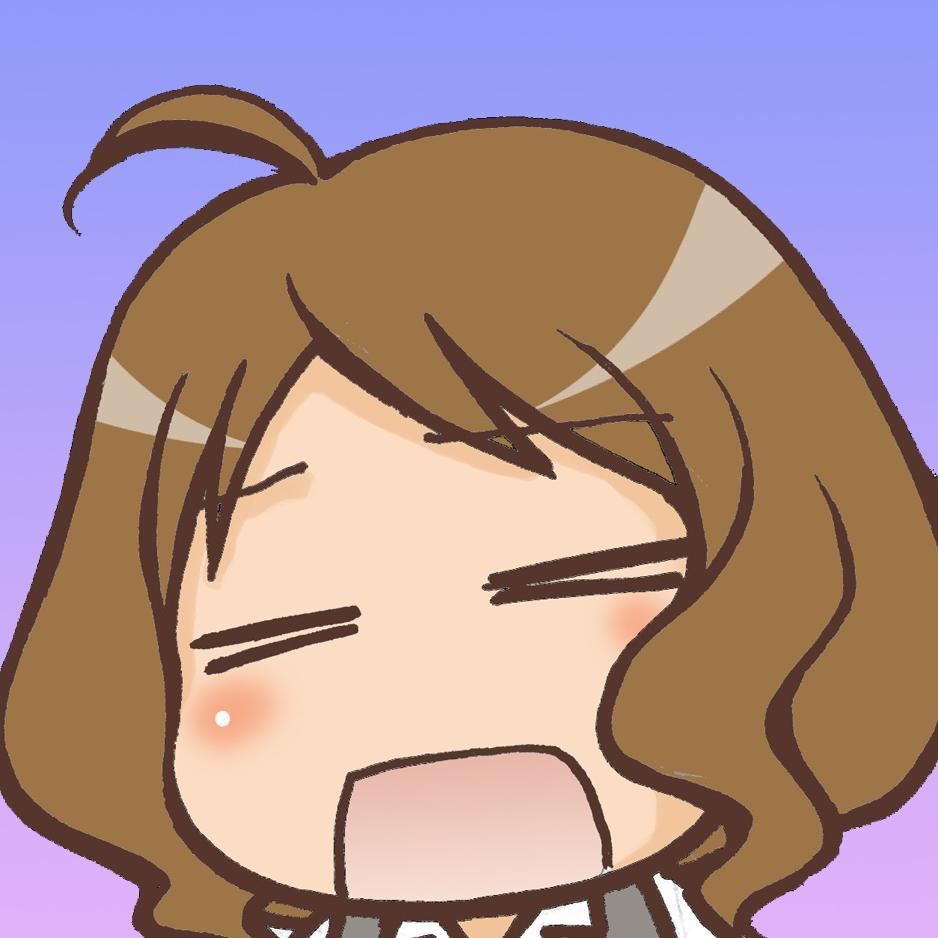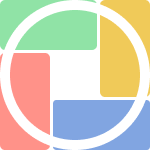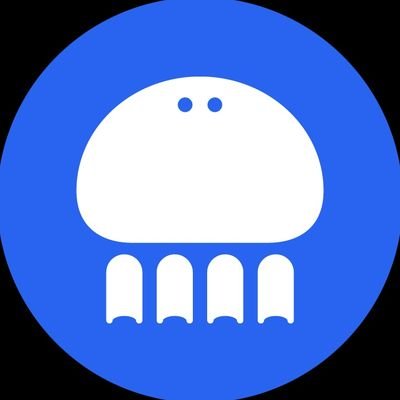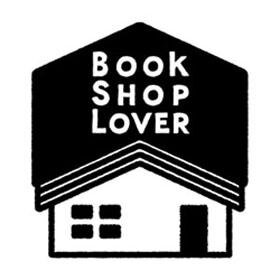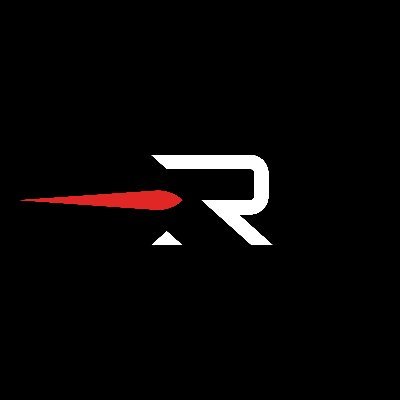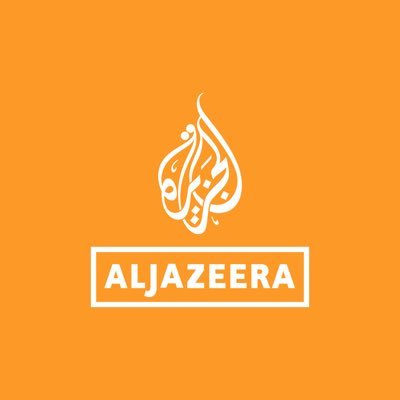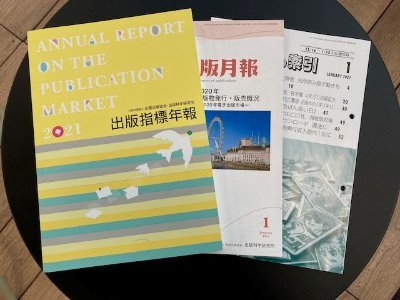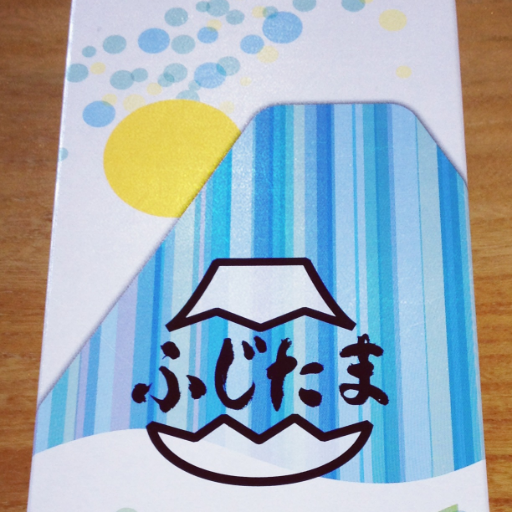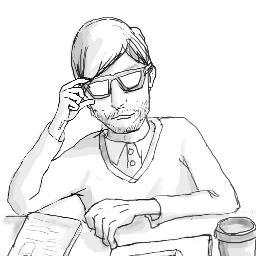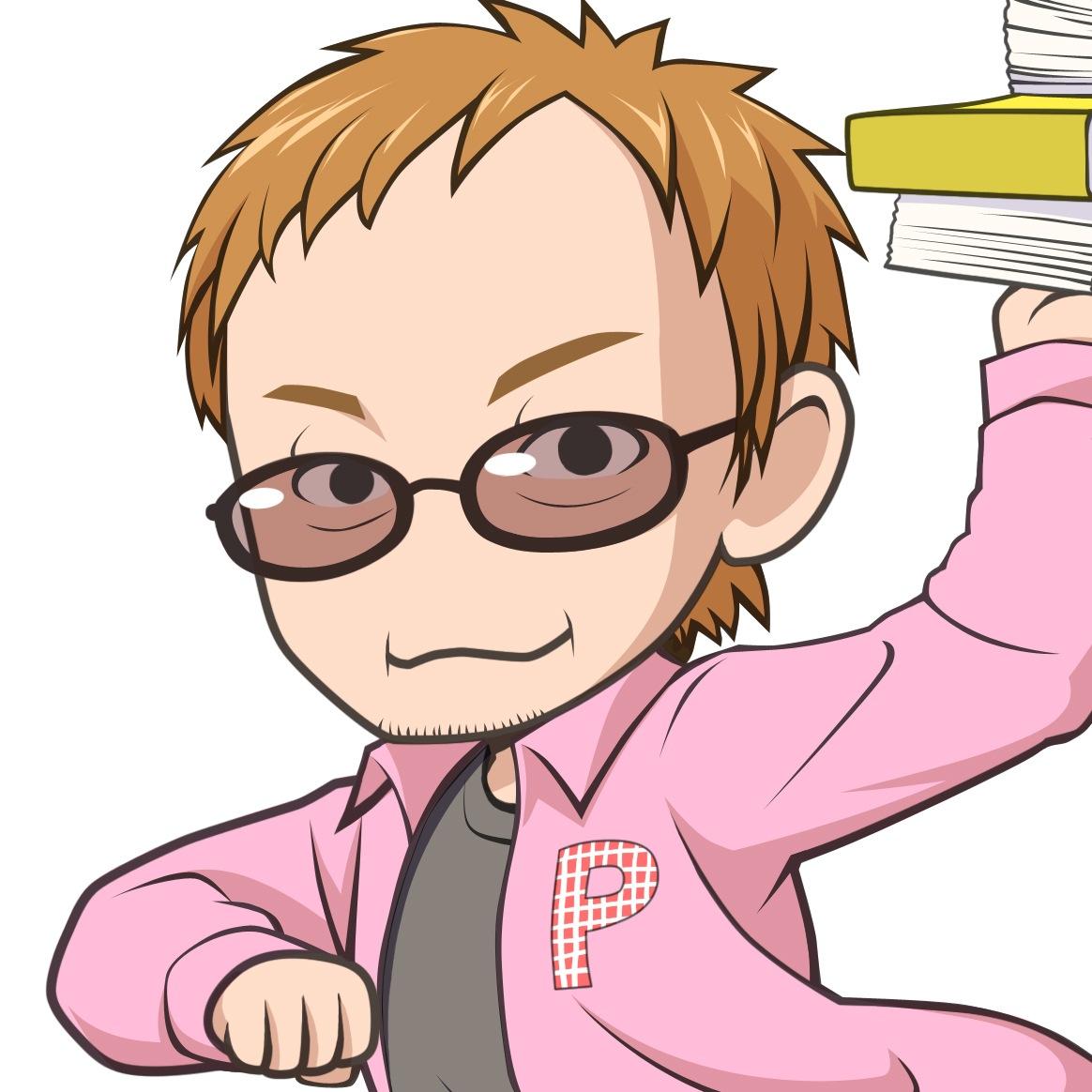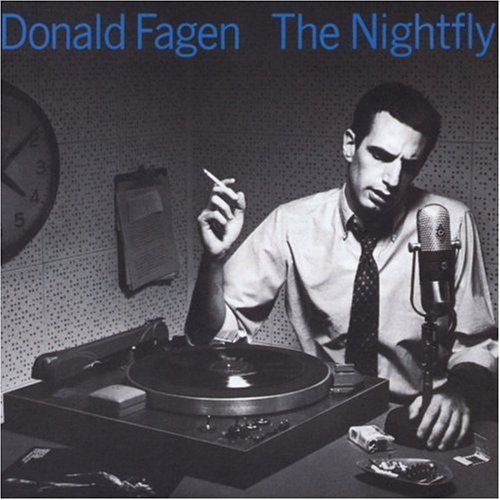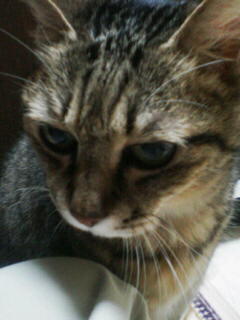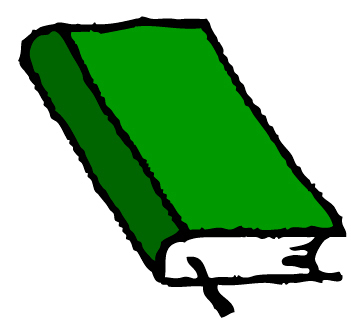TOSH
@takashimt
常に初心者、永遠の周回遅れ(しかも何周も)。
You might like
AI企業売られてるのこれかな 速報:ブルームバーグによると、OpenAIが拡大のために米国政府から資金支援を求めている。 OpenAIは納税者に債務の保証を求めている。彼らは政府に融資の保証(共同署名者のようなもの)を求めている。…
BREAKING: OpenAI is requesting financial support from the US government for its expansion, per Bloomberg. OpenAI wants taxpayers to guarantee its debt. They’re asking the government to guarantee loans (like a co-signer). When private companies start asking for public funds,…

3年前にChatGPT出てから「一体OpenAIはこれでどうやって儲けるつもりなんだ?」ってみんなずっと言ってて、今でも言ってて、そして実際ずっと儲かってなくて投資された金をひたすら溶かし続けてる。そんで2週間くらい前から「実はこれ結局儲からないのでは?」って急にみんな言い出した
他人事とは思えず、購入して拝読中(なお私は病的な「前倒し」派)。 安達未来『締め切りより早く提出されたレポートはなぜつまらないのか 「先延ばし」と「前倒し」の心理学』 (光文社新書、2025年4月)

紙の本を売るためのネットに限らないITの活用は今や基本であり必須になったと言っても過言ではないのだけれど、自分もまだまだ追いつけていませんね。このままやっていても追いつける気がしない。けど、ここで踏ん張らないと。AIも自分はAPIを直接叩いたりして既に製品にも反映させ始めています。
その後の電子コミックの隆盛に関連して「値引き」や「ためし読み(無料もある種の価格施策)」といった販促手法や、流通網としてのネットを意識した広告宣伝については随分と参考にさせていただいております。電子コミックが切り開いた道は紙の本を売るためにも有効だという事実。
「(紙の本の)古い出版業界から(電子書籍の)新しい出版業界への大変革に際して何らかの役割を担うことで古い業界では得られなかった権威なり地位なりを得たい」みたいな空気を醸し出している人もいてある意味で面白かったなあ。変化の時期には必ず胡散臭いヒトが現れるんだな。
弊社は実用書系なので電子教科書が普及すると紙の本の読み方がわからない子どもが増えてくるのではと心配してたけど、どうやらそれも杞憂っぽいんだよなあ。しばらく前からよく聞くタイパとやらの影響で動画や音声より紙の本のほうが箇条書き的で手っ取り早いという考え方もあるようだし。
そしてあの頃「これからは電子書籍と言っている人々がさほど遠くない将来に「紙の本が大事」とか「本屋が大事」と言い出しても自分は驚かない」などとも自分は言ってたんですよ。なんつうか、みんな思い入れが強すぎるというかなんというか。
あのイベントの前後は「出版業界の未来は電子書籍なのに乗ろうとしない出版社は◯◯だ」みたいな論調が大きくうねっていて自分はかなり辟易してたんだよなあ。斜に構えるとかではなく「いや多くの中小零細は電子書籍でそんなに儲けられらないでしょ」というのが自分としての実感だったので。
雪が降ってたのは1回目の時だったかそれとも震災の直前の2回目の時だったかなあ。1回目の記録はポット出版から本になっています。 hanmoto.com/bd/isbn/978478…
むかしまだ電子書籍に夢をもっていた頃、阿佐ヶ谷のロフトAで百人超えのトークイベントをやった。大雪の夜に夜半過ぎまで人が残って本の未来を語り合った。いま、電子書籍の夢は破れてなにも期待してないけれど、あれの軽出版バージョン(即売会ではなく、つくっている人のトークが中心)をやりたいな…
むかしまだ電子書籍に夢をもっていた頃、阿佐ヶ谷のロフトAで百人超えのトークイベントをやった。大雪の夜に夜半過ぎまで人が残って本の未来を語り合った。いま、電子書籍の夢は破れてなにも期待してないけれど、あれの軽出版バージョン(即売会ではなく、つくっている人のトークが中心)をやりたいな…
「リアル書店と出版社の直接取引」の数字はだいぶ昔は推計で出てたかと思いますが、かなり小さかったですよ。「取次を介さない巨大取引!」みたいなのは以前はありませんでした。ですが昨今は大手が某オンライン書店と直接取引しているのでそこそこの数字になっているかもしれません。
そういえば出版関係の統計では「取次を介さない書店と出版社の直接取引の数字は含まない」ことがほとんどです。この注意書きを見て「書店での売上はもっと大きい」と考える方もいるのですが、ここで言う「書店」は確かアマゾンも含んでいますよね。違いましたっけか。
逆に海外はコミックが伸びる余地がある、つまり電子コミックがまだまだ大きく伸びる可能性があるわけで。そりゃあ、大手が海外展開にチカラ入れるわけですよね。
大手は元々コミックと雑誌の比率が高かったところが多いので紙の比率が半分近いとか半分を切っているとか割とリアルな感覚なんだろうと思いますが、書籍専業の小零細はピンと来ないだろうなあ。電子書籍に積極的といってもその多くはおまけ程度の売上だろうし。
コミックと雑誌を除くと書籍のみの出版社には電子書籍に積極的なところも消極的なところもある。消極的なところだと電子書籍の売上比率は7%よりもさらに低いはず。まあ、積極的なところでコミックみたいに電子が7割みたいなことはないはずですが(電子書籍が専業もしくは専業に近いところは除く)。
コミックと雑誌を除外して「紙書籍と電子書籍」に絞って割合を考えると、紙が93%で電子が7%ぐらい。まあ、体感としてドイツとあんま変わんねえんじゃねえかなあ。どうすかね。
わかりにくいのが「コミック」での電子と紙の比率で、紙のコミックは多くが雑誌扱いなので紙の雑誌の数字に含まれている。そして「書籍扱いコミック」というのもある。このあたりはとてもわかりにくい。
United States Trends
- 1. Penn State 23.4K posts
- 2. Indiana 39.1K posts
- 3. Mendoza 20.5K posts
- 4. Gus Johnson 6,861 posts
- 5. #UFCVegas111 5,317 posts
- 6. #iufb 4,252 posts
- 7. Sayin 70K posts
- 8. Omar Cooper 9,665 posts
- 9. Mizzou 3,910 posts
- 10. Iowa 19.9K posts
- 11. Estevao 40.6K posts
- 12. Josh Hokit N/A
- 13. Kirby Moore N/A
- 14. Sunderland 156K posts
- 15. Beck 7,525 posts
- 16. Texas Tech 14.1K posts
- 17. Jim Knowles N/A
- 18. Happy Valley 1,923 posts
- 19. Preston Howard N/A
- 20. James Franklin 9,025 posts
Something went wrong.
Something went wrong.