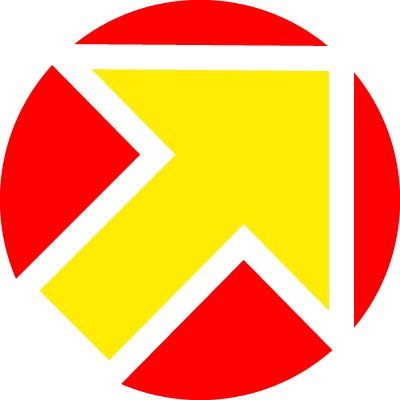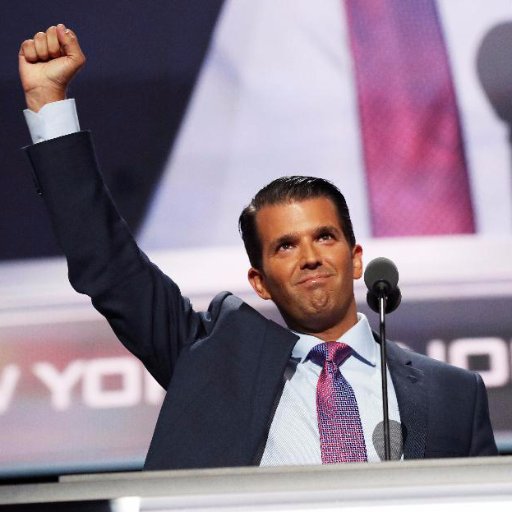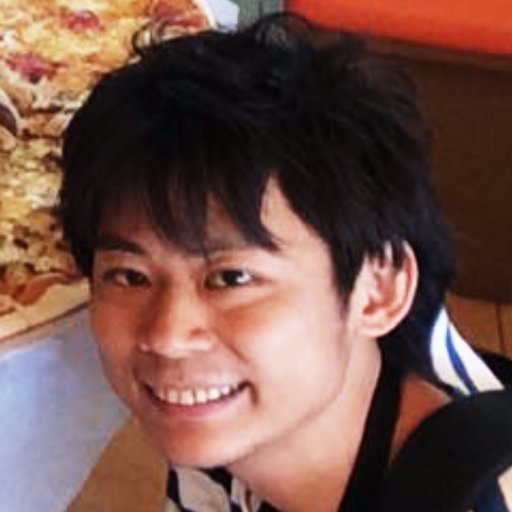【匠×AI #3】 日本のアドバンテージ化について。 厳格基準領域での細部の再現性をAIが担えば、日本の"職人気質"は武器になる。 「観察→要件化→教材化→評価指標→更新」を手順化し、半年で1領域から匠→AI移植に着手する。
【匠×AI #2】 品質と生産性の両立。 これまで“品質か生産性か”のトレードオフに悩んでいた。生成×分析を同時に回すとで個別対応のコストが下がり、品質維持とスループット向上の両立が可能に。 微妙な判断が多い業務から試し、リードタイム/不良率/再作業率で効果を測りながら勝ち型をテンプレ化する。
【匠×AI #1】 職人気質×AIの再現性。 日本の細部まで行き届く品質は強みの一方、標準化に乗せにくくIT化を阻んできた。AIなら細かな判断や例外対応を学習し、”こだわり”を落とさずに仕組み化できる。 まずは現場の暗黙知を洗い出し、プロンプト/ルール/テンプレに分解し、小さく回して精度を上げる。
日本の内製人材の不足について。 IT人材の多くがベンダー側で、自社ITの弱さが改革速度を鈍らせた。正しい要件整理と運用標準が鍵。人材育成の遅れが効率化を阻害している。 内製伴走/運用標準/権限と評価をセットで設計し自走化を目指す。
アクセンチュア独走の背景について。 JVで“自社化”を支援し、BPOまで巻き取る器。独走に納得感がある。 欧米は自社ITが主流で、日本も内製/JVで“わかる側が設計”へ転換。依存度を棚卸し、SLA/移譲基準を再設計、代替PoCを並走する。
【コロナ後の日本の変革 #3】 三つ目は投資の偏重。 今は基幹/ECに投資が集中して顧客接点(Webサイトやアプリ)は手薄。最終的な競争力は顧客の体験差。測定→改善の回転が早い領域。 CVR/CPA/LTVを先に合意して、小さくAB→型が立てば横展開していく。
【コロナ後の日本の変革 #2】 二つ目はIT投資の本格化。 欧米に遅れていた日本でも、22–24年にIT投資が再加速。“DX”というより基盤への再投資、ERP/SAPなどの土台整備が中心。 土台→運用標準→自動化の順でKPIを置き、重い刷新は段階導入。
【コロナ後の日本の変革 #1】 一つ目は大資本回帰の実感。 期待より“実態と信頼”が重視され、資金と案件は大資本へ回帰、ベンチャーには逆風。品質/体制/継続性が評価軸に直結している。 守りは大手で安定、攻めは小回りで。役割線とKPIを先に明文化。
GX(ジェネレーショントランスフォーメーション)について。 高齢化で社会は保守化。世代の転換=Generationの変革が要る。世界に先駆けて日本が取り組み、世界へ輸出していく。
日本のコア技術について。 正攻法でアメリカや中国の技術と戦っても勝てる可能性は低い。 ただ、アメリカや中国が持っていない、かつ理論的にいけそうな技術があれば、ゲームをひっくり返せる可能性はある。真っ向勝負勝負ではなく、コアな技術+飛躍的な可能性にかけて勝負をする。
磁気メモリMRAMの調達と判断軸について。 日本(東北大学)がコア技術を持っている。現状はコストと供給が課題。量産が進めば下がるが、時期は読みにくい。 調達は慎重に。比較指標を決め、段階導入でリスクを抑えて、供給とTCOを見ながら拡張していく。
【日本のコア技術 #2】 磁気メモリMRAMについて。 MRAMは超低消費電力で、省電力の本命候補。量産が進めばAI/エッジ/ウェアラブルの電力制約を緩められ、設計の自由度が広がる可能性。 採用の狙い所を特定して、省電力の恩恵が大きい領域から試作で当てにいく。
NTT IOWNの事業設計について。 技術はあくまで手段。適用領域と連携先、必要スキルの欠落が遅延を産む。 社外アセットと補完関係を描き、自前主義より“連結の設計”が速い。 PoC→限定商用→標準化の段階表と投資ゲートを設定して進める。
【日本のコア技術 #1】 NTT IOWNについて。 日本のコア技術候補。電子から光へ。電力効率100倍、転送量125倍、遅延1/200のポテンシャルがあり、実現すればAI/DCの前提が変わるかも。 PoC候補を洗い出し、適用領域・連携先・必要スキルを事前にマップ化する。 rd.ntt/iown/
United States 트렌드
- 1. Cheney 29.5K posts
- 2. Election Day 82.4K posts
- 3. Logan Wilson 2,777 posts
- 4. Good Tuesday 26.8K posts
- 5. GO VOTE 71.7K posts
- 6. #tuesdayvibe 1,474 posts
- 7. Rolex 15.8K posts
- 8. Halliburton 1,607 posts
- 9. #Election2025 2,204 posts
- 10. George W. Bush 8,229 posts
- 11. Hogg 7,550 posts
- 12. Jerry 47.9K posts
- 13. Tommy Robinson 25.3K posts
- 14. #WeTVAlwaysMore2026 1.49M posts
- 15. Jonathan Bailey 47K posts
- 16. iPads N/A
- 17. Comey 96.2K posts
- 18. WhatsApp 161K posts
- 19. #AllsFair N/A
- 20. Nino 50.1K posts
Something went wrong.
Something went wrong.